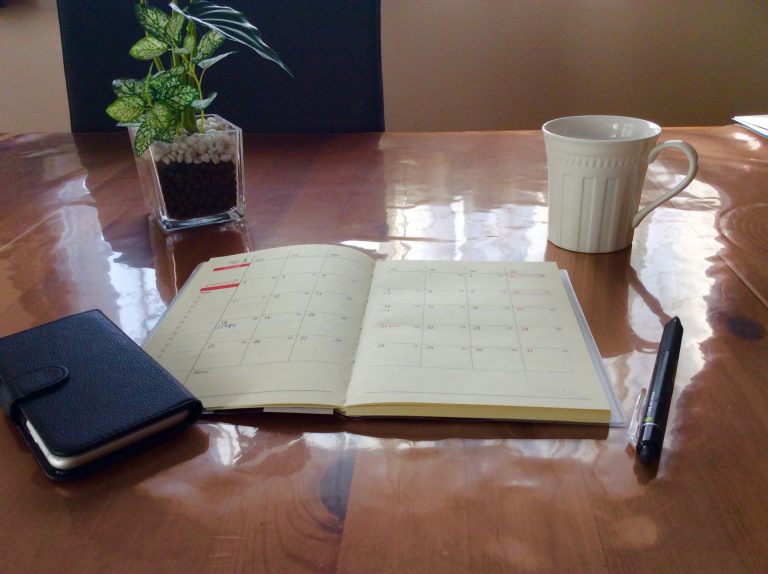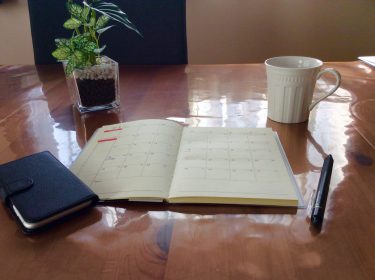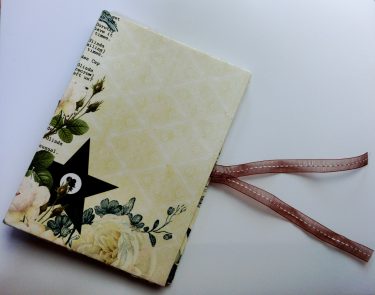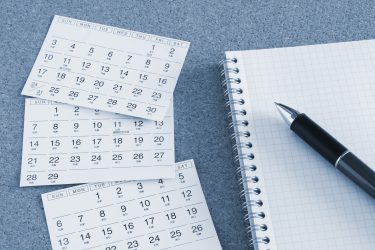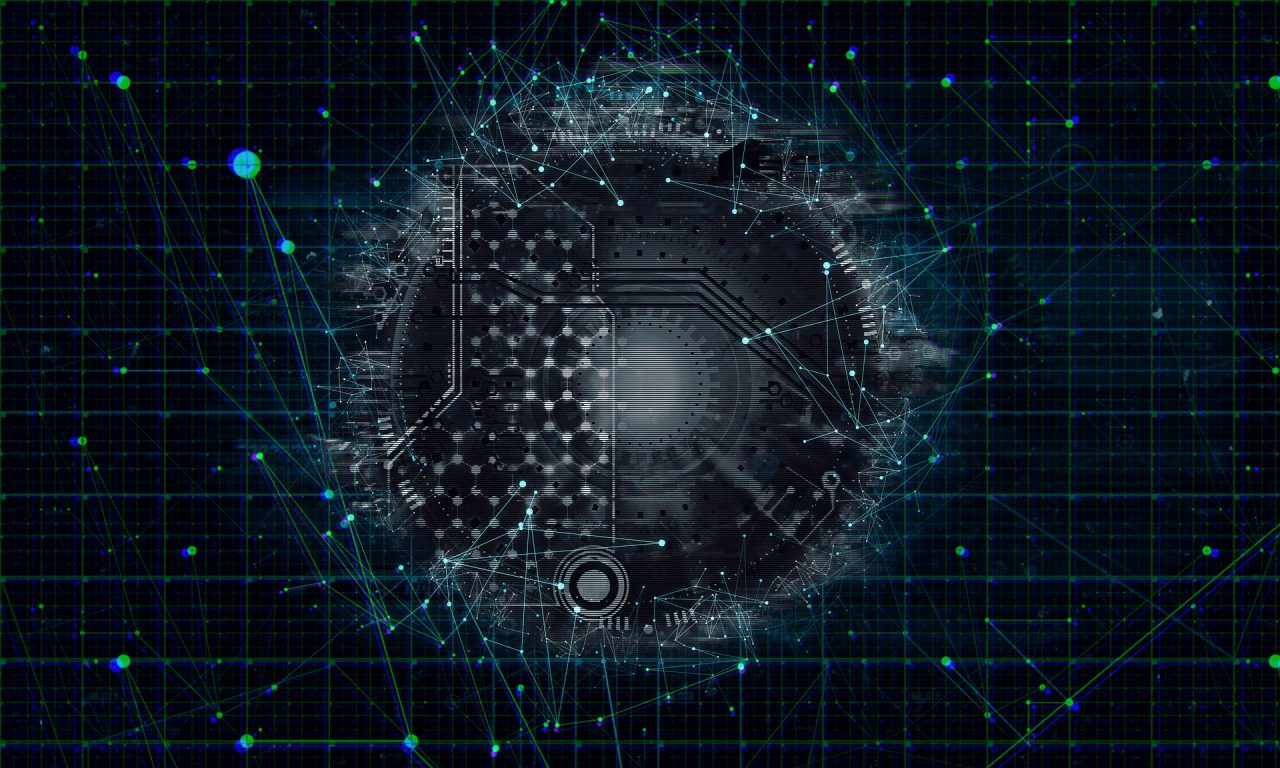初めての電子書籍の出版って難しいですよね。
実際に書き始めると、心が挫けてしまいそうになることもあります。
何から書き始めようかと悩んだり、書きたいことをうまく表現できなかったりといったこともありますし。
うまく書けたかなと思っても、他の人に読んでもらうとダメだったり…。
しかし、実は執筆には、「正しい方法」があります。
これまで文章を書くことに苦手意識がある方でも、ほんのちょっとした執筆の知識やスキルで一気にうまくいくことがあるのです。
今回は、今まで多くの起業家の文章を添削してきた私が、日ごろクライアントにお伝えしていることをぎゅっと凝縮して特に大事なことだけを記事にまとめました。
電子書籍の出版には興味があるけれど、「執筆には自信がない」と思っている方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
なぜ1カ月という短期間で電子書籍を出版できたのか?
なぜ1カ月という短期間で電子書籍を出版できたのか?
ここでは、私が初めての電子書籍を出版するまでの、実際のスケジュールをお話しします。
私は、2020年の2月ころ、新型コロナウィルス感染症の影響で打ち合わせや仕事がどんどんキャンセルとなっていき、時間のゆとりができたものの、今後の経営をどうするのかとても悩んでいました。
そこで、とあるセミナーで電子書籍を出版するメリットについて初めて聞き、今この空いた時間にやろうと決意したのが、3月6日でした。
3月6日には「タイトル」や「目次」「プロフィール」など、本の企画を立てました。
その作業におよそ7時間ほど。
その日の午後から夜まで、集中して取り組みました。
そこから、執筆のための日を2日確保しました。
仕事の予定を全く入れずに、執筆だけをする日を自分の手帳に書き込みました。
その2日間は、朝から晩まで集中して、メールも見ずに取り組み、一旦書き上げました。
書き上げた原稿はスタッフに送り、第三者的にきちんと伝わる文章となっているのか添削してもらいました。
添削期間はおよそ1週間。
他の仕事もあるので、その合間に読んで修正してもらいました。
その間、私は表紙のデザインに取り掛かります。
自分でデザイナーに依頼する前のラフ案を作り、デザイナーに依頼しました。
デザイナーには3月20日頃に依頼して、修正等のやり取りもありながら、3月末に表紙が出来上がりました。
また、今回の私の本の場合は、見込み客リストを増やしたいという目的があったため、特典を準備する必要があります。
電子書籍の特典としては、動画が相性がいいのではないかと思い、動画を収録・編集し、また、申し込みページや読者限定ページなどの制作を行いました。
スタッフからの修正原稿に、最終的に少し加筆をし、3月中に原稿が完成。
私の場合は、ワードで原稿を制作していたので、そのデータをe-pub形式に変換する作業を外注に依頼しました。
その出来上がりが4月6日で、4月7日にキンドルに登録、その日の夜に出版となりました。
短期間で電子書籍を出版するための5つのポイント
このように、私の場合は初めての電子書籍の出版ではありましたが、1カ月で出版までこぎつけることができました。
なぜ、1カ月間でできたのか、そのポイントを5つ紹介しますね。
(1)出版までの方法を教えてもらった
一番大きいのは、実際出版した人にきちんとやり方を教えてもらったことです。
初めてのことは、あなたも一緒かもしれませんが、何から手を付けたらいいかわからないものです。
なので、その順番や外したらいけないポイントを教えてもらうことは、成功への近道だと思います。
(2)締め切りの設定とスケジューリング
いつまでに出版すると締め切り日を決めなければ、ずるずると先延ばしになってしまいます。
私がサポートしているお客様にも、まずは出版日を決めるようにアドバイスしています。
出版日が決まると、そこから逆算して、いつまでに何をする必要があるのかスケジュールが組むことができます。
漠然と「何月ころに出版しよう」というよりも、
「●日に企画をたてて、●日までに一旦書き上げて、●日にはデザイナーに依頼して・・」
など作業ごとに日付を決めていくことで、具体的な行動につながります。
なにも短期間で電子書籍を出版する必要性はありません。
ですが、私が実際自分で出版してみて思うのは、「やるぞ!」と集中して一気に書き上げるという勢いも大事だなと思います。
(3)執筆と編集を分ける
執筆はアクセル、編集はブレーキと言われたことがあります。
アクセルとブレーキを同時に踏むと、非常に効率が悪いです。
ですので、書くときは書くことに専念して、あとで編集するようにした方がいいですね。
また、書くネタや順番はあらかじめ自分の中で決めてから執筆したほうが、迷わず一気に書くことができます。
その役割を果たすのが、目次作成です。
目次を作りながら「第3章にはこのネタでいこう」など全体のイメージを先に作るのです。
先にそれを考えておくことで、執筆に集中でき、早く書くことができます。
(4)音声入力を使う
一からすべての文字を入力するのは大変です。
そこで、私の場合はグーグルドキュメントの音声入力を使っていました。
目次を決めてから、その内容についてセミナーを開催したつもりや、お客様に説明しているつもりで、話をするとそれがテキストに変換されます。
そのテキストを編集していくイメージです。
音声入力をすでに使われている方もいらっしゃるかと思いますが、まだの方はこの機会に一度使ってみてください。
非常に便利ですよ。
(5)第三者に読んでもらう
自分の書いた文章がきちんと伝わるかなという不安は、最初はだれにでもあるものです。
自分では、いろんな前提を当然知っている中で書いているので、他の人からしたら意味がよくわからない文章や、なんで急にこの展開なのか?といった点が出てきます。
そういった点に不安を抱えながら執筆すると、なかなか筆が進みません。
はじめから、「きちんと伝わるかの不安」を捨てることが大事になってきます。
そうするためには、第三者に読んでももらうことを前提に執筆すればいいのです。
もちろん、初めての人にもきちんと伝わるように心掛けて書くことは大事です。
しかし、しょせんはそこは自分にはわからないことなので、他人に読んでもらって、
「どこが読みにくいのか」
「どこがわかりにくいのか」
「どういった要素があったらもっと良くなるのか」
といった観点でフィードバックをもらうということが決まっていれば、安心して執筆を進めることができます。
私の場合もスタッフにダメだしされることを前提で書いていましたので、何度も「ここはどういう意味ですか?」と聞かれました。
そのプロセスが、執筆の速度を速める安心感へとつながります。
おわりに
一人で悩んで、あれこれ無駄な努力をして、かけがえのない時間を失うのではなく、特に最初は、正しい順番で正しい方法で電子書籍の出版に取り組んで欲しいと思います。
そのために、この記事が少しでもお役に立てればと思います。